「空飛ぶクルマって本当に飛ぶの?」「大阪万博ではいくらで乗れるの?」そんな疑問を持つ方へ。本記事では、大阪万博2025における空飛ぶクルマの展示内容、搭乗可否、気になる料金情報、さらに今後の実用化に向けた最新情報までを完全ガイド。未来の交通手段をいち早く体感したいあなたに、見どころと注意点をわかりやすく解説します!
空飛ぶクルマってそもそも何?万博での役割は?
空飛ぶクルマの定義と国内導入状況
「空飛ぶクルマ」とは、正式には**電動垂直離着陸機(eVTOL:electric Vertical Take-Off and Landing)**と呼ばれ、ドローン技術と航空機技術を融合した次世代モビリティです。電動モーターを使用し、垂直に離着陸できるため、都市内移動や空港アクセスなどでの活用が期待されています。
日本国内では、国土交通省が「空の移動革命に向けたロードマップ」を発表しており、2020年代中に商業運航を目指す動きが加速しています。これまでの車や電車に続く「第4の移動手段」として、今後のインフラ整備や法制度の整備も進行中です。
万博での展示目的とコンセプト
大阪・関西万博において、空飛ぶクルマは単なる未来技術の紹介ではなく、次世代都市交通の象徴として位置づけられています。「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとする万博では、空飛ぶクルマがどのように社会に溶け込み、私たちの生活を豊かにしていくかを来場者に伝えるための体験型展示が行われます。
この展示には複数の企業が参加しており、機体の実物展示や映像体験、離着陸のデモンストレーションなどを通じて、「未来の空の移動」がどのようなものかを視覚的・体感的に知ることができます。
実際に飛ぶ?模型だけ?
万博では、実際に空を飛ぶデモンストレーションが予定されています。特設ステーション「Vertiport」では、企業が製造した空飛ぶクルマが一定のタイミングで飛行する様子を見学できます。ただし、これは来場者が乗ることを目的としたものではなく、機体の動作確認や未来イメージの共有を主目的としています。
誰が開発している?参画企業紹介
主な参画企業には、日本の「SkyDrive」、米国の「Joby Aviation」、ドイツの「Volocopter」などがあり、いずれも世界で注目されるスタートアップや大手企業です。これらの企業はそれぞれ特色ある機体を展示しており、エネルギー効率や乗車人数、安全設計などを比較しながら楽しめるのも魅力の一つです。
万博以降の実用化スケジュール
空飛ぶクルマは、2025年の万博以降に本格的な社会実装を目指しています。関西空港~夢洲間での「空の移動サービス」構想や、都市内での短距離移動、災害時の緊急搬送など、さまざまな応用が期待されており、2030年頃には一部有料運行がスタートすると予測されています。
大阪万博で空飛ぶクルマに乗れるの?料金は?
搭乗の可否について公式回答
結論から言うと、大阪万博2025では空飛ぶクルマに乗ることはできません。公式FAQにも明確に記載されており、空飛ぶクルマはあくまで「展示・デモンストレーション用途」であり、一般来場者が体験搭乗できるイベントではないことが明言されています。
これは安全性・法的整備の観点から判断されたもので、初の大規模公開の場としての展示にとどまる形式となっています。
チケット販売はあるのか?
「乗ってみたい」「いくらなのか知りたい」と思う方も多いですが、搭乗用のチケット販売は一切行われていません。今後、商業化が進んだ際にはチケット制度が導入される可能性は高いですが、万博の段階では見学のみとなります。
そのため、「空飛ぶクルマの料金」という意味では、万博では具体的な価格設定はありません。
搭乗料金の想定と参考価格
ただし、実用化が進んでいる他国の例を参考にすると、1人あたり10,000〜30,000円程度が初期価格帯と予想されています。これは短距離移動(5〜15km程度)を対象とした場合のもので、タクシーよりやや高めだがヘリコプターよりは安いという位置付けになります。
将来的には需要や法整備が進むことで、さらに価格が下がる可能性もあり、公共交通と同等になるには2035年以降と見る専門家も多いです。
代わりに体験できるサービス
万博では、実際に飛ぶ空飛ぶクルマを見る以外にも、VRシアターや没入型映像体験などが用意されています。特に「空飛ぶクルマ ステーション」では、視覚と音響によって実際に乗っているかのような仮想体験が可能で、こちらは事前予約制となっています。
体験は座席型・スクリーン型の2種類があり、利用者の満足度も高く、子どもやシニア層でも楽しめる内容です。
なぜ乗れないのか?安全面の背景
空飛ぶクルマは、法的には「航空機」に近い扱いとなるため、搭乗には運航許可・操縦資格・安全検証など多くの要素が関わります。現在はそれらの整備中であり、一般来場者を乗せるにはまだリスクが高いと判断されています。
したがって、万博での空飛ぶクルマは“未来の社会を想像するためのデモンストレーション”という位置付けなのです。
空飛ぶクルマが見られる場所はどこ?展示の楽しみ方
「空飛ぶクルマステーション(Vertiport)」とは
大阪万博2025で空飛ぶクルマを実際に目にできる場所は、会場北西側に設けられる特設エリア「空飛ぶクルマステーション(通称Vertiport/バーティポート)」です。ここは空飛ぶクルマの離着陸や展示、体験型映像コンテンツなどが集結した空専用の未来モビリティ展示ゾーンとなっています。
ステーション内では、安全エリアが確保された状態で来場者がデモフライトを見ることができるほか、企業ごとの機体展示や仕組み紹介などもあり、子どもから大人まで楽しめる構成です。
デモ飛行のスケジュールと場所
デモ飛行は不定期で実施され、1日に数回程度、指定時間に機体が離着陸する様子を公開します。具体的な飛行時間や機体スケジュールは当日現地での案内または万博アプリで通知される仕組みです。
飛行デモは短時間(数分間)で行われますが、実際に浮き上がる様子や、回転ローターの迫力、静音性などを間近で見られる貴重な機会です。
混雑を避けたい場合は、午前中の早い時間帯や雨天時を狙うと比較的スムーズに見学できます。
どの会社の機体が飛ぶ?特徴紹介
現在予定されている主な機体と企業は以下の通りです:
| 企業名 | 国 | 機体名 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| SkyDrive | 日本 | SD-05 | 1人乗り/軽量設計/短距離飛行向け |
| Joby Aviation | アメリカ | Joby S4 | 4人乗り/商業化最前線/静音性高 |
| Volocopter | ドイツ | VoloCity | 都市向け2人乗り/EV/垂直離着陸可能 |
| Vertical Aerospace | イギリス | VX4 | 長距離/5人乗り/高速度 |
これらの機体は実際に万博会場で離陸・着陸する姿を見学でき、将来の空の移動を体感できる貴重な展示になっています。
写真撮影はOK?SNS映えスポット
ステーションエリアでは写真撮影が可能です(フライト中は安全のため距離制限あり)。機体を背景にした撮影スポットや、企業ロゴ入りのフォトフレームも設置予定で、SNS映え間違いなし。夜間ライトアップバージョンの展示も予定されており、夕方〜夜にかけては幻想的な雰囲気になります。
ステーション内の予約制コンテンツとは?
ステーション内には、没入型体験ブース(VR/シミュレーション映像)があり、これらは事前予約制です。空飛ぶクルマに実際に乗っているかのような映像体験ができるコンテンツで、座席に座ってヘッドマウントディスプレイを装着し、360度の映像や風・音響による臨場感を楽しめます。
小学生以上が対象のブースも多く、ファミリーでの体験にもおすすめです。公式アプリまたは会場内のQRコードでの予約が必要なので、早めに確保しましょう。
デモフライト以外の見学方法と混雑対策
展示シアターとVR体験の内容
空飛ぶクルマステーションでは、デモフライトだけでなく、「展示型シアター」や「インタラクティブ体験ゾーン」が設置されており、機体に乗らなくてもその世界観を十分に楽しめる内容になっています。
シアターでは、空飛ぶクルマが実現する未来の都市、空路ネットワーク、交通の進化などを大画面で紹介。音響や振動、映像演出により臨場感たっぷりの演出が魅力です。
VR体験では、ヘッドセットを通して実際に操縦席に座っているかのようなシミュレーションを体験できます。操縦操作こそできないものの、上空からの視点で都市を眺めながら移動する感覚は非日常そのもの。
会場内ルートとアクセス方法
空飛ぶクルマステーション(Vertiport)は、会場の北西エリアに位置し、「スマートモビリティエリア」内の一角として整備されています。夢洲駅からは徒歩15分ほど。案内板やアプリマップを確認しながら向かうとスムーズです。
ベビーカーや車いすでもアクセス可能で、スロープや手すりの設置も万全です。
混雑予想とベストな見学時間帯
空飛ぶクルマ展示は、午前10時〜午後2時が最も混雑しやすい時間帯です。逆に朝9時台と夕方16時以降は比較的空いており、ゆったりと見学できます。
また、週末や祝日は特に混雑が予想されるため、平日の朝が狙い目です。混雑予測は万博公式アプリでも確認できるので、来場前にチェックするのがおすすめです。
子ども連れや高齢者でも安心の楽しみ方
VR体験や映像展示は着席スタイルが多く、小さなお子さんや高齢者でも安心して楽しめます。館内には授乳室や多目的トイレも完備されており、家族連れでも安心して利用可能。
また、ステーション付近には日陰の休憩スペースやドリンクスタンドも設けられており、暑さ対策や待機時間の調整にも便利です。
雨天やトラブル時の対応は?
空飛ぶクルマのデモフライトは、天候や風速、機体整備状況により中止になることがあります。その場合でも、展示シアターやVR体験は屋内で実施されるため、楽しめるコンテンツに困ることはありません。
雨天時の案内は会場放送や公式アプリで通知されるため、傘・レインコートなどの準備と併せて、アプリの通知をONにしておきましょう。
万博後の空飛ぶクルマはどうなる?未来展望
関西空港~夢洲の空路構想
万博終了後、空飛ぶクルマの実用化に向けた具体的な取り組みとして注目されているのが、関西国際空港〜夢洲間の空路構想です。地上交通の混雑を回避し、国際空港と都市部を10分以内で結ぶ高速ルートとして、政府や自治体、民間企業が連携して準備を進めています。
この構想は、インバウンド観光客の利便性向上だけでなく、災害時の緊急輸送ルートとしても活用できる可能性があり、2025年万博が大きな節目になると期待されています。
2030年以降の国内導入スケジュール
国土交通省の「空の移動革命に向けたロードマップ」によると、2030年前後には都市部での有償運航を開始することを目指しています。初期は観光地や島嶼部での実証運航からスタートし、徐々に都市部へ拡大する形が想定されています。
大阪をはじめ、東京湾岸地域、名古屋、福岡など、人口密度の高い都市圏では空港アクセスや通勤用途としての導入が検討されています。
通勤や観光に使われる未来の交通手段
空飛ぶクルマは、将来的には通勤・通学・観光に使われる「空のタクシー」として活用されることが期待されています。渋滞を回避し、短時間で目的地に到達できる利便性から、都市間移動の新たなスタイルとして脚光を浴びています。
特に観光地では、空中からの景色を楽しみながらの移動が可能になり、移動自体がアクティビティとなる時代が来るかもしれません。
空飛ぶタクシーの実現可能性
アメリカ、中国、ドイツなどでは、すでに空飛ぶクルマを活用した「空飛ぶタクシー」の試験運用が始まっています。日本でも、自治体と企業が連携してタクシー事業者との共同実験を行う計画があり、2030年代中には一般利用が現実になる見通しです。
課題は、騒音・安全性・コスト・離発着場所(Vertiport)の整備などがありますが、万博をきっかけにその解決に向けた動きが加速しています。
今後の料金モデル予測
将来的に運用される空飛ぶクルマの料金モデルは、「距離×時間×燃費(エネルギー消費)」に加え、「離発着地の使用料」や「天候対応プレミアム」なども含まれると予想されています。
初期は1回あたり1万円前後が想定されていますが、技術の普及と量産が進めば、数千円程度での利用も可能になると考えられています。月額定額サービスやビジネス専用プランなど、多様な形態での提供も検討されており、「空飛ぶ定期券」のような形も登場するかもしれません。
まとめ
大阪万博2025では、未来の交通手段として注目される「空飛ぶクルマ」を間近で見学できる絶好のチャンスです。ただし、現在のところ来場者が実際に搭乗することはできず、搭乗料金は未設定となっています。
その代わりに、空飛ぶクルマステーションでのデモフライトやVR体験、映像シアターなどが充実しており、視覚・聴覚を使ってその世界観を楽しむことができます。事前予約が必要な体験コンテンツもあるので、万博公式アプリを活用してスケジュールを立てるのがコツです。
また、空飛ぶクルマは万博後も実用化に向けた動きが加速する分野であり、将来的には関西空港や都市間での利用、さらには観光・通勤の「空の移動手段」として日常に取り入れられる可能性も十分にあります。
「今はまだ乗れない」からこそ、今見ておく価値がある空飛ぶクルマ。大阪万博で一歩先の未来を体感してみませんか?

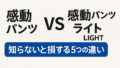
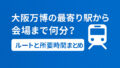
コメント